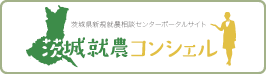農地を貸したい、借りたい
農地を貸したい方
1.相談、申出
各市町村の農地中間管理事業担当(農政担当等)窓口までご相談ください。
出し手(農地の所有者)は、「貸付希望申出書」に必要事項を記入の上、市町村農政担当窓口に提出してください。
受け手(耕作希望者)は、借りたい農地の条件等について市町村農政担当窓口にご相談ください。
2.状況確認
貸付希望農地の状況を確認します。(現状、面積、権利関係、希望賃料など)
3.マッチング
貸借条件について、出し手及び受け手の双方が合意したときには、農用地利用集積等促進計画を作成します。
4.利用権の設定
農用地利用集積等促進計画の認可・公告により機構での農地中間管理権(利用権)が設定されます。
5.賃借料の精算について
農用地利用集積等促進計画で定められた賃借料の精算(徴収・支払)は金納(口座振替、口座振込)を原則とします。
なお、物納や現金支払いによる設定は可能ですが、賃借料の精算については出し手と受け手が直接行うものとし、機構は関与しない(責任は負わない)こととしています。
出し手のメリット
- 原則、賃借料は機構から口座振替により支払われます。
- 契約情報(農地を誰に貸しているのか、賃料はいくらなのか)がきちんと残ります。また、農地相続後も安定した契約が維持できます。
- 契約期間(利用権)が満了すれば、農地の利用権は出し手に戻りますが、希望すれば契約更新ができます。
- 納税(相続税・贈与税)猶予の適用を受けている場合、税務署への手続きを行うことで猶予が継続されます。
- 農業者年金を受給中の方は、引き続き受給できます。
- 契約中に受け手が病気等で耕作出来なくなった場合、地域計画内では原則、地域内の話合いによって次の受け手を決めますが、もし決まらない場合機構は市町村等と協力して周囲の耕作者とマッチングを行い、次の受け手を探します。(最長1年間。但し、借受基準に満たない農地については、その限りでない。)

受け手のメリット
- 長期の耕作(経営計画)が可能となり、経営の安定化が図れます。
- 賃借料(金納)は口座振替により機構に支払うため、支払事務が軽減できます。
- 地域の話し合い等により、まとまった農地の借受や分散した農地を集約することができます。
- 契約中に受け手が病気等で耕作出来なくなった場合、地域計画内では原則、地域内の話合いによって次の受け手を決めますが、もし決まらない場合機構は市町村等と協力して周囲の耕作者とマッチングを行い、次の受け手を探します。
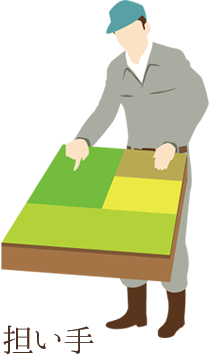
借受希望申込書
- 借受希望申込書様式第3号
- 借受希望申込書(記載例)様式第3号
貸付希望申出書
- 貸付希望申出書様式第6号
畑の集約化について
境木(隣接する畑の境界、目印)の替わりにマーカーを埋設することで境木の撤去による畑の大区画化を図り、担い手農家へのさらなる農地の集積・集約化を目指します。