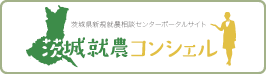品目別振興対策協議会のご紹介
県域生産出荷組織等において、研修会や検討会等を開催するとともに、活動を運営・支援し、本県園芸組織の体制強化、活動を図る。
茨城県梨組合連合会
 会長 糸賀 和則
会長 糸賀 和則
①会長あいさつ
茨城県梨組合連合会 会長の糸賀和則でございます。
当連合会は、なし栽培技術の向上や販売流通対策に取り組むことにより、「茨城県産なし」の評価を高め、梨経営の向上につなげることを目的に活動している団体です。現在(令和7年5月)、19の組合・513名のなし生産農家が加入しております。
本県のなしは、栽培面積・収穫量とも全国第2位(令和5年)、県西、県南、県北地域を中心に栽培されています。主要な品種は、「幸水」「豊水」「新高」「あきづき」ですが、県オリジナル品種「恵 水 (けいすい) 」の栽培も増加しており、恵水は、大玉で糖度が高く贈答用としても期待されています。
また、今年度から、当連合会加入生産者へ、県オリジナル新品種「ひたちP3号」の苗木供給もはじまります。
連合会の活動としては、高品質栽培に取り組むための栽培講習会や出荷規格を統一するための出荷目揃(めぞろ)い会の開催、さらに、県内メディア巡回(各新聞社、12社)など、各種PRにも取り組んでいます。
今後とも茨城の美味しい梨を皆様にお届けしたいと存じます。
当連合会の活動に対し、引き続きご理解とご支援をお願いいたします。
茨城県くり生産者連絡協議会
 会長 田口 一彦
会長 田口 一彦
①会長あいさつ
茨城県くり生産者連絡協議会 会長の田口一彦でございます。
当協議会は、本県くりの生産拡大・販売改善等により、くり生産農家の経営安定を図ることを目的に平成9年に設立された団体です。活動としては、栽培講習会や現地研修会等を通じて会員相互の交流と栽培技術の高位平準化を図っています。
本県のクリは、栽培面積、収穫量、産出額ともに全国第1位の産地となっております。また、最近はケーキの「モンブラン」がブームとなっており、国産クリは収穫後、すぐに加工できることで風味に優れるペーストが作れるため、加工業者の引き合いが強くなっており、実需者の県産クリへの期待は大きくなっております。
しかし、日本一のクリ産地である本県においても、担い手の高齢化と減少、樹の高樹齢化が進んでいることから栽培面積と収穫量は年々減少しており、産地の将来が危惧されているところです。
当協議会としましては、「儲かるくり経営」を目指し、関係機関と連携しながら省力的な収量・品質の向上技術、収穫作業等の機械化等による労働生産性の向上、県産くりのPRと需要拡大に取り組んでいきたいと考えておりますので、ご支援とご協力をお願いいたします。
②会員構成及び令和6年度会員数
5組織(JA部会:3、専門農協:1、任意組合:1)、510名。
茨城県施設園芸研究会
 会長 中澤 清
会長 中澤 清
①会長あいさつ
茨城県施設園芸研究会 会長の中澤 清でございます。
当研究会では、県等関係機関と連携しながら収量・品質の向上のための栽培技術の研鑽や最新技術の情報共有、県内外での研修会や立毛品評会等を開催しています。
近年、施設園芸分野においては、ICT等を活用した高度環境制御装置の開発と普及が急速に進んでおり、光合成理論に基づいた作物の生育に好適な環境を与えることで、特に、トマトやキュウリにおいては飛躍的に収量が向上する結果が得られております。
そのため、当研究会においてもITCを活用した環境測定装置を導入し、施設内環境の「見える化」を行い、従来の温度と湿度でだけでなく、光合成に必要な炭酸ガス濃度や光量もデータ化し、環境改善の研究に取り組んでいるところです。
当研究会は県域の研究会でありますので、国や県、メーカー等の最新の技術や地域を超えた会員の優良経営事例など、得られる情報も多く、仲間づくりの場としても機能しております。
施設園芸を取り巻く環境は、燃油や生産資材価格の上昇などにより生産コストが増加し、たいへん厳しい状況にありますが、県等関係機関やメーカー、会員で知恵を出し合いながら「儲かる施設園芸経営」の実現に向けて研究会活動を展開していきます。
②令和6年度会員構成
12支部 77名
茨城県野菜養液栽培研究会
 会長 栁澤 浩二
会長 栁澤 浩二
①会長あいさつ
このたび、茨城県野菜養液栽培研究会長を拝命しました栁澤浩二でございます。
当会は設立から32年目(平成6年設立)を迎え、現在、県内の養液栽培生産者23名、賛助会員9社、特別会員6機関が所属しております。会員の栽培品目は葉菜類と果菜類で多種にわたり、会員の多くが法人化しています。
農業経営を取り巻く環境は、生産資材価格や人件費の上昇、気候変動による生産の不安定化など、引き続き、たいへん厳しい状況にあり、農家が生き残っていくためには様々な創意工夫が必要となっています。
当会では、会員の技術及び経営向上のため、令和6年度の活動として福岡県での先進事例研修、神栖市での技術研修会などを開催いたしました。
また、令和4年度からは施設園芸セーフティネット構築事業(燃料価格高騰対策)への加入を希望する会員を対象に当会が申請者となって会員の経営支援を行っているところです。
当会としましては、県等関係機関と連携しながら経営の参考となる先進地視察研修会、生産性・品質向上のための最新技術を学ぶ技術研修会を開催し、養液栽培ならではの消費者・実需者に喜ばれる野菜生産と儲かる経営を研究していきたいと考えておりますので、関係機関の皆様には御支援・御協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
②会員構成及び令和6年度会員数
・正会員(23名):野菜養液栽培の生産に従事するもの、または将来においてこれを志向する者及び学習者等。
・賛助会員(9社):本会の主旨に賛同し、支援するもの。(生産資材メーカー等)
・特別会員(6名):野菜養液栽培の研究事業に携わるもの及び施設野菜の生産出荷を指導する団体の担当部署長等。
【正会員が栽培する主な養液野菜】
サラダ野菜、みつば、バジル、くうしん菜、チンゲンサイ、サンチュ、こねぎ、トマト、パプリカ、イチゴなど
茨城県かんしょ生産者連絡協議会
 会長 川﨑 卓男
会長 川﨑 卓男
①会長あいさつ
茨城県かんしょ生産者連絡協議会 会長の川﨑 卓男でございます。
本県の令和4年のかんしょ産出額は361億円であり、全国1位の地位にあります。近年、日本のかんしょはスイーツとしても国内外で人気があり、国内だけでなく海外での需要も増しております。一方で、気候変動や品種改良により寒冷地での栽培も可能となっていることから、県産かんしょのより一層の品質向上とブランド力強化に取り組んでいく必要があります。
令和6年産は、昨年同様、記録的猛暑により高温・乾燥条件下での栽培となり、収量への影響は少なかったものの、立枯病や黒斑病等が昨年より多く見られた年でした。今後は、気候変動に対応した栽培方法や担い手の高齢化と減少に対応した省力的な栽培方法が求められます。当会としましては、県等関係機関と連携しながら技術情報の
共有や優良事例等を学ぶ研修会等を開催し、「儲かるかんしょ経営」につながる活動を展開していきたいと考えておりますので、関係機関の皆様には引き続き、御支援・御協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
②令和6年度会員構成
8部会・組合 370名
茨城県いちご経営研究会
 会長 鷺谷 一雄
会長 鷺谷 一雄
①会長あいさつ
本県は、いちごの生産量全国7位ですが、京浜地域ではシェア12%を占めており、主産県の一つです。直売所・いちご狩り園は100か所以上あり、県産いちごをお気楽にお求めできますのでぜひご利用ください。
近年は、各県とも県オリジナル品種が育成されるなか、本県オリジナルの「いばらキッス」は市場評価も高いことから、県と一緒になって生産拡大、品質向上に努めております。
また、県全体のいちご振興と生産者相互のレベルアップを目指し「茨城いちごグランプリ」や、県と一体とたったいちごのPR販売などを開催しております。
さらには、県内のいちご直売所・いちご狩り園のパンフレットを作成し、県内の道の駅や直売所等に配布するとともに、県のホームページにも掲載しPRをしております。
茨城県いちご経営研究会のこれら活動に対し、関係機関の皆さまのご支援をお願いし、ごあいさつといたします。
②会員構成(会員数290名)
JAいちご生産部会、生産団体、個人生産
茨城県ぶどう連合会
 会長 阿久津 浩
会長 阿久津 浩
①会長あいさつ
茨城県ぶどう連合会 会長の阿久津 浩でございます。
当会の会員数は27組織・個人で219名(令和6年12月現在)であり、県内ぶどう生産者の半数以上が加入しています。また、後継者や若手生産者による青年部も組織されており、現在23名で活発に活動しており、先進地視察研修や首都圏でのPR販売、青年部主催で「第3回シャインマスカット果実品評会」を開催し、積極的に活動しております。
本県のぶどうは、ほとんどが直売(観光直売)による販売であり、会員が現在栽培している品種は「巨峰」が全体面積の5~6割程度と減少傾向にあるのに対し、近年は価格を牽引している「シャインマスカット」を中心に多種多様な欧州系品種の導入が進んでいます。
令和6年産は、昨年同様、猛暑の影響で着色不良や肥大不良などの高温障害が目立ちました。また、県内全域でカメムシ類の発生が非常に多く、対策に苦慮した年でした。
当会としましては、県等関係機関と連携しながら技術講習会・現地研修会等の開催、人材育成研修への参加促進、青年部の活動支援を行い、生産基盤の強化、消費者ニーズに応える品種の導入推進、若手生産者の育成につなげ、会員の「儲かるぶどう経営」の実現を目指していきたいと考えております。
関係機関の皆様には引き続き、御支援と御協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
②令和6年度会員構成
27組織(197名)、個人会員(22名) 計219名